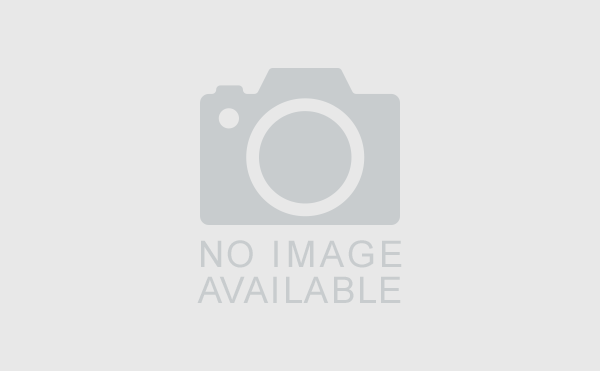農家にマーケティングは必要? 規模別に見る「はじめどき」
Q:農家もマーケティングを意識するべきなの?
A:普通に売るだけなら、マーケティングは不要です。
農協以外の販路をどう考えるか
農業の良いところとして、作れば売れる点があります。日本には農協があるので、多くの場合は作れば売れます。例外はもちろんあるのですが、製造業やサービス業から見れば販売ハードルはかなり低いです。だから、農家にとってマーケティングは絶対に必要というわけではありません。
ただし、高く売りたい場合、経営を安定させたい場合には、マーケティングは必須です。規模別に、農協以外の販路を考えていくべきタイミングを考えてみましょう。
全ての農家にマーケティングが必要なわけではない
マーケティングを意識しなくて良いのが、農業の良いところです。法的には卸売市場法には受託拒否の禁止が定められていますし、規格内であれば農協が買い取ってくれます。例外を挙げればキリがないですし、満足のいく買取価格ではないことも多いですが、しかし、基本的には作れば売れるのが農業です。
「作れば売れる」のは、普通の産業ではまず考えられません。私たち経営専門家がどれだけ技術を磨こうとも、農家さんに相手にされなければ商売は成り立ちません。農家から野菜を買い取る小売店でも、お客さんが来なければその野菜をお金を払って破棄します。せっかくの自然の恵みを廃棄したい店長は1人もいませんが、マーケティングに失敗したら廃棄せざるをえないんです。
高く売るなら、マーケティングは必要
農業では、「作れば売れる」仕組みを最大限活用して、目の前の農作業に集中できる環境が整っています。全ての農家さんにマーケティング視点が必要かと聞かれたら、「なくてもいい」というのが私の意見です。特に就農直後や生産量が小さいときは、販売は農協に任せて農作業に集中するのも大いにアリです。
ただし、自分が作った農産物を高く売るためには、マーケティングは必要です。マーケティングを成功させることで、市場卸売価格の何倍もの値段で農作物を販売している農家さんはたくさんいます。千葉県産のネギの今日の市場価格は1kgあたり387円で、1本あたりざっくり50円。しかし、「うちは生産方法にすごくこだわって、お金もめちゃめちゃ掛けている。それを値段にも反映させたい。1本250円で売りたい」と考えるなら、マーケティングが初めて必要になります。
マーケティングの「はじめどき」
マーケティングを意識すべきタイミングとしては、年間の売上高3,000万円~5,000万円が挙げられます。
なるべく高く売りたいというのは誰しもが思うことですが、高く売るためには相応のコストが掛かるもの。店舗訪問や販売活動に時間とお金を掛けられるかどうかが分かれ目です。感覚的な話で恐縮なのですが、売上高3000万円あたりになると農作業とマーケティングを両立させられる会社が多くなるように思います。
たとえばネギの場合、1ヘクタールあたりで30トン弱くらい採れます(千葉の場合です)。5ヘクタールなら130トンくらい。これに卸売価格を掛けると5000万円くらい。農家さん側の実際の手取りは、諸々引かれて4000万円台前半です。もちろん土地や作目によりますが、売上3,000~5,000万円といったときの規模感としての参考にしてください。
これくらいの規模になると、フルタイムの従業員を雇い、繁忙期にはパートの方もたくさん雇い入れます。経営者の方は、農作業現場から離れる時間を多少は確保できます。
また、一定の生産量もあるので、小売店さんや卸売業者さんとの深いお付き合いも始められます。身も蓋もない言い方をすれば、交渉力が付きます。
遅くともこれくらいのタイミングが、マーケティングの「はじめどき」です。ちなみに、系統出荷から直卸に切り替えても、価格が一気に上がるケースはあまり聞きません。ただ、販売価格の交渉はできるので、市況リスクを緩和する効果はあります(分かりやすく言えば、豊作時でも買い叩かれづらくなる)。
「農家」から「経営者」へ
規模感はあくまでも例であって、結局は企業としての考え方や財務状況次第ではあります。農地を借りる前からマーケティングありきで戦略を立てていた農家さんもいて、その方は規模は追求せず、素敵なライフスタイルを手に入れられています。ただ、上述したくらいの規模感であれば、マーケティングに割ける余力が出てきます。その時が1つのチャンスです。
早く始めた方が良いと言い切れないのもマーケティングの難しいところではあるのですが、「経営者」としての一歩を踏み出したのであれば、マーケティングは優先順位が高い領域です。「うちの状況ってどうなんだろう」「もしかして販売に時間を使いすぎ?」と思った際はお気軽にご相談ください。売上規模別に、今やるべき販路選定や価格戦略などを一緒に考えます。