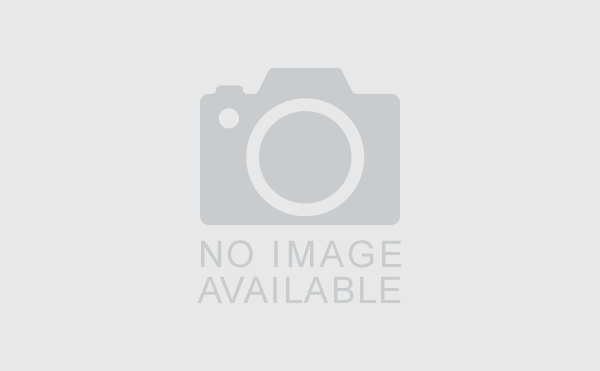Q:損益計算書って、どこを見ればいいの?
A:売上原価と販管費に注目します。
決算書は、今後の経営にも活かせる
決算書は、税理士に任せっきり。でもせっかく作ったのだから、経営にも活かしてみませんか?
損益計算書から分かるのは、①なぜ儲かったのか(過去)だけではありません。②どうすればもっと儲かるのか(未来)のヒントが、損益計算書にはたくさん詰まっています。本記事では、農家が損益計算書を「経営判断に活かす方法」をやさしく解説します。
損益計算書からは、利益が生まれた理由が分かる
損益計算書とは、会社がどれだけ儲かったか(あるいは損をしたか)を表すものです。実践形式で説明するので、ご自分の損益計算書を引っ張り出してみてください。紙のものでも、PDFでも構いません。
損益計算書の一番上に書かれている「売上高」ってありますよね。これが1年間の販売額の合計です。そこから費用や税金を引いたりして、会社に利益として残る金額が、一番下に表示される「当期純利益」です。
「売上高」はたくさんあったはずなのに、「当期純利益」を見たらかなり少ない(もしくはマイナス)ですよね。潤沢だった売上高が、当期純利益の金額まで痩せ細ってしまった原因が書かれているのが損益計算書なんです。
損益計算書を見るときの肝は、一番上に書かれている売上高の数字が、なぜ一番下の当期純利益になったら減ってしまったのか(もしくは、なぜあまり減らずに残ったのか)を読み取ることです。そのうえで、来年度以降は減ってしまわないように対策を講じたい。だから対策を講じるべきポイントを見つけましょう、というのが損益計算書の分析です。
損益計算書で見るべきポイントは、とりあえず2つ
損益計算書を分析するための準備をしてみましょう。やっていただくのは、2つのことです。①2年分の損益計算書を準備してください。②日本政策金融公庫の「農業経営動向分析結果」をダウンロードしてください。以上、2つの準備を終えたら、分析を始めていきましょう。
損益計算書を見るときは、まずは左端のところを見ます。【売上高】とか【売上原価】とか書いているところです。
この中で、特に注目すべきポイントは、【売上原価】と【販売管理費】です。売上原価というのは、農作物を作るために掛かった費用です。販売管理費というのは、農作物を売ったり、会社を経営するために掛かった費用です。売上原価と販売管理費の分析は、来年度以降の経営にきっと役に立つはずです。
この2点をどのように分析すればよいか、続いて解説します。
売上原価の分析
「売上原価」の分析でやることは2つです。1つ目は、売上高との比較、2つ目は昨年実績と業界平均との比較です。
農作物を作るために掛かった費用である売上原価は、売上高が伸びたら売上原価も伸びるものです。売上の伸びに引っ張られる形で増大していく費用を「変動費」と呼ぶのですが、売上原価は変動費のような性質を持っています(正確には、労務費や減価償却費は除きます)
そこで、売上原価と売上高の割合を計算します。損益計算書の中で売上原価の金額を見つけてください。「売上原価」や「売上原価 計」の右側の数字がそれです。たとえば3000万円と書かれているとしましょう。その数字を、売上高の金額(仮に5000万円とします)で割ります。4000万円÷5000万円なので、0.8つまり80%です。この値を「売上原価率」と言います。これを、2期分、計算してみてください。たとえば前期の売上高が4500万円で売上原価が3500万円だった場合、前期の売上原価率は77.77777%です。
続いて、業界平均との比較を行います。もしあなたが梨の生産者(法人)だったら、先ほどダウンロードした「農業経営動向分析結果」p.35の果樹法人のデータを見ます。そこから先ほどの要領で計算した結果、売上原価率の業界平均は71.033%と分かりました。
この場合、当期の売上原価率は80%で、前期は約78%なので、売上原価率は悪化しています。また、業界平均は約71%なので、平均と比べても悪い数字です。
そうすると、なぜ売上原価率が悪いのかが気になりますよね。そこで、内容を考えていきます。
売上原価の分析で分かること
内容を考えるためには、「製造原価報告書」があれば便利です。決算書を1枚ぺらっとめくると、「製造原価報告書」がついていることがあります。「製造原価報告書」には売上原価の内訳がすでに書かれているので、それを2期分見比べながら、「どれが増えちゃったのかな~」と考えていきます。同じ要領で、業界平均とも見比べながら、「どこが膨らんでしまっているのか」を探していきます。
考えるときのコツは、「大きいところから考える」ことです。微妙な数字の違いに着目したところで、それを改善するかどうかは経営に大きな影響を与えません。その意味では、昨年度との比較はそんなに意味がないことになります。なぜなら2%しか変わっていないからです。でも、業界平均とは9%も違うので、何か大きなポイントが隠れているかもしれません。
一例として、肥料や農薬などからなる「材料費」を検討してみましょう。仮に、売上高に占める割合が30%だったとしたら、業界平均の12.67%を大きく上回っていて、もはや異常です。となると、肥料の見直しや減農薬の工夫を他の農家さんから学ぶべきなのかもしれません。
ここまで分かれば、次の行動はすぐに思いつきます。たとえば肥料会社さんに相談したり、他の農家さんに聞いてみたり、JAの人に聞いてみたり。来年は肥料費をぐっと抑え込むことで売上原価率を改善し、利益を確保したいところです。
販売管理費の分析
続いて、農作物を売ったり、会社を経営したりするための費用である「販売管理費」を見ていきましょう。
「販売管理費」に含まれるのは、農協に出荷した際の販売手数料や、社長自身の役員報酬、Webサイトなどを作る広告宣伝費などがあります。売上高が上がっても割合はそんなに変わらないことも多いので(販売手数料は別)、数字を単純に見比べていきます。
たとえば、昨年の販売管理費が800万円、今年の販売管理費が700万円なら、今年は100万円の削減に成功したということになります。
販売管理費の分析で分かること
販売管理費を見る際に気を付けたいポイントは、「減りすぎていないか」です。
意外かもしれないのですが、私がコンサルティングをするときに販売管理費を減らせとはあまり言いません。むしろ、「販売にもっと力を入れた方が良い」「人材確保に注力すべき」と助言することの方が多いです。
その理由は2つあります。1つ目は、給料や福利厚生費、研修費などを削ると会社の雰囲気が悪くなるからです。売上高とは関係なく一定金額かかる費用を「固定費」(「変動費」の反対)といいまして、販売管理費は固定費のような性質に近いです。そういった固定費は削減はしやすいんですが、削減すると雰囲気が悪くなりやすい費用でもあります。なんというか、観葉植物のような感じです。オフィスに置いてある観葉植物って、必要ではないけれど、雰囲気が良くなるじゃないですか。固定費は働いてくれる人への愛でもありますし、明るく前向きに仕事をするための原動力でもあるので、無理をして削るものではないと私は思っています。
2つ目の理由は経営的なもので、販売管理費の削減は、長期的には販売力の低下につながるからです。広告宣伝費や採用教育費などは、未来への投資です。販売管理費は費用なので、削減すると利益につながることは事実です。ただ、来年・再来年の売上が下がってしまうのは避けたいので、販売管理費の削減には慎重になった方が良いと思います。その意味で、販売管理費が昨年よりも下がっているなら、「販売力の低下につながっていないかな」と注意してみておくことが重要だと考えています。
結論 損益計算書を経営に活用しましょう
ここまで見ていただいた通り、損益計算書から分かることはすごく多いです。売上原価と販売管理費に着目しましたが、実際にはその他にも見るべきポイントはたくさんあります。たとえば、本業以外にも収入源があれば、それはリスク分散による安定的な経営につながりますが、それがうまく行っているかどうかは営業外収支に書かれています。
また、本文で紹介していない見方もたくさんありますし、本文で紹介した見方は分かりやすさを重視したので、もっと精密・正確に見る方が本当は良いです(それでも、見ないよりは全然良いです)
最後に宣伝です。今、「財務分析パッケージβ版」を1万円にて試行的にご提供しています。決算書3期分をお送りいただくことで、財務的な面からの長所や短所、注意すべきポイントなどをパワーポイント5枚程度でお送りするものです。「次の投資をしていいのか迷っている」「借入金が膨らんでいて、ちょっとだけ不安」「財務は考えたことがないので一度プロの目からどう見えるのかを教えてほしい」といったご要望にお応えできるかなと思って始めたサービスです。良ければご検討ください。