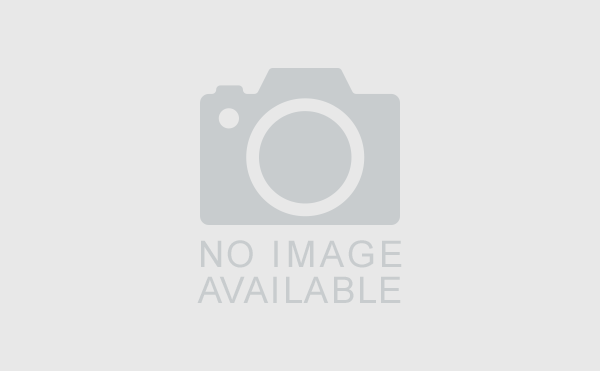農業のマーケティング戦略は、どのように作ればいいの?
Q:マーケティング戦略づくりって、何から始めたらいいの?
A:消費者を理解することから始めます。
マーケティング戦略とは
マーケティング戦略とは、農作物や加工品をたくさんの人に適正価格で買ってもらえる仕組みを整えることです。学術的な定義では「人間や社会のニーズに応えることで他者から望ましい反応を引き出すための枠組み」となるんですが、平たく言えば、「売れる農産物を作りましょう。作った農産物を適正価格で売りましょう。そのためには準備が必要ですよね」という考え方です。良いマーケティング戦略を立てることで、言い値で売れるようになったり、過剰な売り込みが不要になったりします。
①消費者を理解する
マーケティング戦略は、世の中の消費者を理解することから始めます。自分の感覚だけで世の中の消費者を理解したつもりになるのではなくて、どんな食べ物が売れているのか、誰が何を何の目的で買っているのかを考えます。日本全国の市場の中で、たとえば千葉の家族はどんな野菜・果物を買っているのか。有機野菜にこだわりを持っている人は全体の中でどれくらいいるのか。千葉に旅行に来る人は、千葉県でどんなものを食べ、どんなお土産を買っているのか、などを考えます。いわゆる市場調査のことです。
なぜ消費者理解が大事なのか。それは、あなたが作る良いものを、相応の値段で買っていただくためです。悪いものを高く売ってやろうというのはダメですが、コストを掛けて作った良いものを相応の値段で買ってもらうのは商売として当然のことです。
「みんな、何を食べたいんだろうか」「千葉に来る人が買いたいお土産って何だろう」と真剣に考えることが、マーケティングの第一歩。消費者のことを知り、消費者のことを考えることからマーケティングは始まります。
②その中で、誰に何を売れるかを考えます
次に、「千葉の家族」や「千葉に来る人」という主語を絞り込んでいきます。誰もが満足するものって引きが弱くて、結局誰にも刺さらない(=求めてもらえない)ことが多いからです。
「買ってくれるなら誰でもいい」「うちの野菜の魅力を1人でも多くの人に伝えたい」気持ちはもちろん分かります。しかし秋元康も「記憶に残る幕の内弁当はない」と言っているように、誰でもいいから買ってくれと叫んでも買い手は中々現れないものです。「埼玉から旅行に来た35歳の女性に向けて作った〇〇」というイメージで商品を作れば、「埼玉から旅行に来た35歳の女性」には買ってもらえるはずです。
誰でもいいから買ってくれたらいいなと願っても、あなたが望むような公正な価格で買ってもらうことは難しいでしょう。一生懸命作った農作物を適正価格で買ってほしいなら、「誰なら買ってくれそうかな」を考えるのが良いです。
③取引先の人・企業が喜ぶことを考えます
さらに、消費者以外の人にとっての利益を考えることも重要です。いくら良い果物を作って高値で買ってもらえたとしても、作る過程で隣人の圃場を汚染させてしまってはダメですよね。関わる人全てに利益をもたらすことがビジネスの鉄則です。
マーケティングで言えば、特に重視しなければならないのが取引先です。自分の野菜を扱ってくれる卸売業者、飲食店、道の駅、農協などですね。一緒に頑張ってくれる人がいなければビジネスは成り立ちません。その企業や担当者のメリットを考えることも、マーケティング施策の1つです。
たとえばスーパーに直卸をするなら、「定質・定量・定価格・定時」は原則です。問い合わせのお電話をいただいたら数コール以内に出る。出られなかったら折り返すなどは基本動作です。
守らなければならないルール・マナーは多いですが、マーケティングではある種のメリハリをつけていくことも大切です。ビジネスで貴社とコラボしてくれる協力者との関係性を系統立てて考えていきましょう。
④自社がやりたいこと・できることを考えます。
最後に、自社のことについて考えます。
消費者の方が買いたいモノ・コト、取引先が喜んでくれそうなモノ・コトに対して、自社の圃場・会社が何を提供できるのかを見定めます。消費者満足・協力者満足に向けて足りない部分はどこか、自社にしか出せない強みや価値はどこにあるのかを考えていきます。
自分の強みは何で、課題は何なのか。安定した数量なのか、シーズンを外した出荷なのか、加工しやすい農産物なのか、ここでしか食べられないアイスクリームなのか。いくら儲かれば良いのか、どれだけのコストを掛けられるのか。
繰り返しになりますが、自分のことを考えるのは最後です。消費者→協力者→自社の順に、消費者起点で考えていくのがマーケティングの原則です。大まかな流れとしては、マーケティング戦略はこのように作るのが良いです。
ワンポイントアドバイス
戦略立案の時間は限られているので、絶対にやった方がいいことと、後回しでも良いことを分けて考えることは大切です。経営計画に時間を掛けすぎてしまい、圃場の生産性が下がってしまっては本末転倒なので。経営計画は専門家を活用して効率的に立案しつつ、農業に全力投球するのが大切です。
後回しでも良いことの代表例として私が考えているのが、競合分析です。競合分析というのは、自分と同じような商品を、自分と同じお客さんに売っている競合他社を調べること。「互いに代替性の高い製品・サービスを供給する他社」の①戦略②目的③強み・弱みを解明して戦略グループにまとめて整理することで、余計な競争を回避するとともに仮想敵に勝ち抜ける戦略を立てるのが競合分析です。
たとえば市場が限られていて競争を避けられない場合には競合分析は重要になってきますが、そうしたケースは現実的にはそれほど多くありません。むしろ、競合に勝つことばかりに注力して、お客様が求めることに応えられないことの方がよほどリスクが大きいです。
もちろん、必要となれば競合分析のご支援もさせていただきますが、基本的には顧客起点のマーケティングが最優先事項です。お客様に喜んでもらうこと、地域の経済や社会の役に立つことが王道だと言えます。