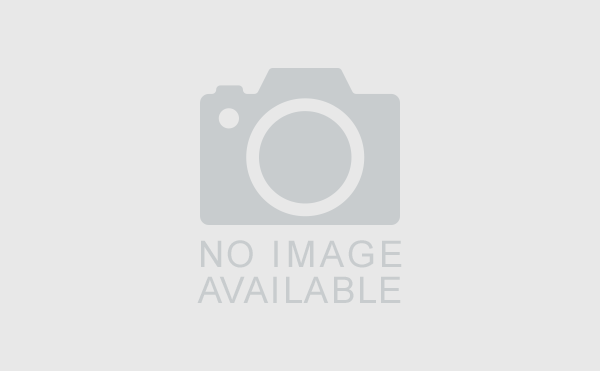道の駅で農作物を売るためには何をすればいいの? 基本から応用までを徹底的に説明します
Q:道の駅で農作物を売りたいんですが、秘訣は何かありますか?
A:消費者が喜ぶ商品を、道の駅の人が喜ぶ形で売ることに尽きます。
道の駅で、農作物を売る
全国1230か所にある道の駅には、日々たくさんの観光客が訪れます。農家さんにとっては、販路を拡大するチャンスです。道の駅だけでかなりの金額の売上を上げている農家さんも実際にいます。直販に少しでも興味があるのなら、道の駅での販売はぜひチャレンジしていただきたいです。
道の駅で販売したい――何から始める?
道の駅で販売するハードルは、比較的低いです。道の駅に問い合わせれば申請用紙などの案内をもらえるので、それに従って登録するだけ。小売店や飲食店相手だと、営業を上手に掛けて担当者を口説き落とすといったステップが挟まってきますよね。道の駅相手ならそれが全く必要ないというわけではないですが、直販の中ではハードルが低い(=参入障壁が低い)とは言えるでしょう。
しかも、うまくいけば結構な売上につながるケースもあります。これは、①道の駅の集客力が強い②商品単価を自分で決められるためです。誤解を恐れずに具体的な数字を出すと、かなりうまく行けば1000万円前後、現実的に狙う売上高は数百万円、といったところでしょうか。道の駅に詳しい研究者※によると「農産物とその加工品で年間1000万円以上も売り上げている農家もあった」とありますから、1000万円あたりに売上高の天井だと考えられるでしょう。インターネットを調べると1500万円くらい売り上げたケースも見つかりましたが、当面の目標は数百万円に設定するのが妥当かと思います。直販のスタートとしては悪くない数字でしょう。
※ 関満博、酒本宏編、2011年『道の駅――地域産業振興と交流の拠点』
道の駅のもう1つの魅力としては、販売手数料の低さが挙げられます。地域振興を謳っている公的な機関(運営は民間だったりもしますが)なので、農家側にとっては力強い味方です。販売手数料は道の駅ごとに、また品目ごとに違うのですが、10%台後半に設定しているところが多い様子。ただし、全量買い取りしてもらえるわけではなく、売れ残り分はこちらが負担する「消化仕入」が主なので、廃棄損を踏まえると利ザヤはもう少し減ります。それでも販売手数料が10%台というのはかなり力強くて、民間ではあまり聞かない低水準です。
農家から見れば、①参入障壁が低い②売上を立てやすい③手数料は少ない、のが道の駅です。直販を考えている農家さんにとって道の駅は、外せない選択肢になってくるはずです。
道の駅が求めるものとは? 単なる売り場ではなく、ビジネスパートナーとして捉えよ
ただし、道の駅で売上を立てつづけるのは簡単なことではありません。考えることはいくつかあるのですが、絶対に外してはならない鉄則をまずは書いていきます。
外せない鉄則、それは、道の駅の運営者と良好な関係を築くことです。道の駅は単なる売り場ではなくて、ビジネスパートナーであり、ある種のお客様でもあるという意識を持つことが重要です。分かりやすく言えば、「売らせてくれてありがとう」とあなたが言うだけでなく、「売ってくれてありがとう」と道の駅に言ってもらえるように努力しましょう、ということです。
そのためには、あなたのビジネスパートナーである道の駅は、何に喜び、どんな課題を抱えているのかを考えなければなりません。そこで道の駅のことを少しだけ深掘りしてみましょう。
道の駅の歴史は、建設省が1988年に設置した豊栄パーキングエリアと、島根県掛合町(現雲南市)が1990年に設置した掛合の里から始まりました。1993年には正式登録が開始され、産業や交流の拠点として1230か所(2025年時点)に広がっています。
道の駅が果たす機能としては、①休憩場所の提供②道路情報や観光情報などの情報発信③地域振興につながるような地域の連携強化、の3つがあります。ただし、こうした機能を果たすのは道の駅だけではなく、他の種類の直売所や民営のレストラン、お土産屋さん、あるいはコンビニエンスストアとも競合しているのが現状で、道の駅の3割くらいが赤字だと言われています。また、生産者の高齢化を受けて、野菜や果物などの農産物を集めることも課題となりつつあります。
ここから考えられることは何でしょうか?
まずは、独自性のある野菜を生産することでしょう。その地域でしか採れない野菜や、その地域ならではのストーリー性のある果物を提供する体制を整えることが重要です。
「そんなこと、言われなくても分かっている」という方は、少し待ってください。良く耳にする話としては、「独自性=他の農家との差別化」を第一に挙げる話を聞きますが、そうではありません。私が言う独自性というのは、他の地域にはない独自性のことです。その地域ならではの独自性を出すのだから、「独自性=他の地域との差別化」です。他の農家さんを押しのけて売るために独自性を出すのではなくて、道の駅をビジネスパートナーとして盛り上げるために独自性を打ち出していくんです。競争よりも共創というのは使い古された言葉ですが、それでも経営・マーケティングの基本です。
また、もう1つ良くある誤解として、安全かつ独自性のある農作物を作って終わりではありません。大切なのは、消費者の方にそれを理解してもらうことです。「こだわって作る」だけでなく、「こだわっていることを伝える」ことも、農家さんの大切な役割です。
だから、ポップは当然、こちら側で作りたいですよね。観光客が喜んでくれるような文章を書いたり絵・写真を貼ったりしましょう。あなたが届ける商品によって、道の駅を盛り上げて地域を活性化していくんです。
また、安全は第一です。農薬の使用状況などを記録した栽培履歴は真面目に付けて、いつでも提出できるようにしておけば駅長さんは安心してくれます。道の駅と同じ理念を持って商品開発を進めていきましょう。
結論としては、「売るのは道の駅の役割だろう」と突き放していては、ビジネスパートナーにはなりえません。売上を維持しつづけられる可能性は下がりますし、他人から妬みを買ってしまっては面白くありませんよね。道の駅(もっと言えば、店舗の責任者である駅長さん)の負担を減らしてあげて、道の駅と一緒に地域を盛り上げていくんです。
消費者が求めるものとは
ここまで大きなことを書いてきたので、もう少し生臭いというかリアルなことも書いておきます。それは、商品の売り方です。実際の売上が付いてこないと話が進まないので、「売れる商品を作って」「きちんと売る」方法も書いていきます。この辺りは実際の売れ行きを見ながら、また道の駅の駅長さんとも相談しながら決めていきます(消費者の声を聴くのが本当は良いんですが、道の駅のシステム的にあまり現実的ではないので、駅長さんの声から消費者の好みを推察します)
①包装の仕方にこだわる
袋に入れるなら、清潔感のある透明な袋を用意するのが原則です。鮮度の低下を防ぐために、袋の口を開けるならきれいに開ける、葉物野菜なら袋から飛び出さないようにする。朝の10時に来るお客様にも、夕方4時半に来るお客様にも、手に取ってもらえるような包装を考えます。
ばら売りする野菜や果物を袋に入れるかどうかはケースバイケースですね。袋に入れたら汚れ防止や鮮度保持の効果はありますが、その分の価格をお客様にご負担いただかなければならないなどデメリットもあります。仮に個別包装はしなくても、モウルドトレーなどは用意しておくと安心感はありますね。夕方に来たお客様が、台に直置きされている残り3つくらいのハクサイや梨を買いたいかというと、あまり手に取りたくはないはずです。これがモウルドトレーに載っているだけでも印象はだいぶ変わります。
商品説明にこだわる
ポップを置くことを禁止されていないなら、ぜひ作りましょう。
①その作物がどんな特徴があるのか(=なぜ美味しいのかを説明します)
②誰が、どうやって作ったのか(=あなたのことと、圃場のことを書きます)
③どんな想いで作ったのか(=経営理念や地域との関わりを書きます)
といった内容を盛り込みます。
その他にも、すごく大きなナスや曲がったキュウリ、黄色いスイカなど、スーパーでは見かけない見た目のものを販売することもありますよね。その場合には、
④なぜその色や形をしているのか、
⑤スーパーの規格品に比べて味はどのように異なるのか
を書くのも良いと思います。
また、その産地でしか採れない珍しい作物などについては
⑥なぜ、他の地域では採れないのか(=なぜ、この地域、圃場では採れるのか)
⑦どうやって食べるのがおすすめなのか(煮びたしにして夕食にもう1品か、低カロリーでお腹には溜まる間食として食べてほしいのか。珍しいが故に食べ方が分からないので)
などは書いておきたいですね。
安全には徹底的にこだわる
観光客の人が商品をせっかく買ってくれたなら、あなたの農園やその地域のファンになってもらいたいですよね。そのためには、「お米に石が混じっていた」とか「トマトを齧ったら中身が腐っていた」などということは絶対に避けなければなりません。食べ物を売る限り、安全は何を差し置いても最優先事項です。
特に気を付けたいのが異物混入。たとえば虫が入っていたら、それは大問題になりかねません。「仕方ないよね」で済まないのが難しいところです。異物混入でよくあるのが髪の毛です。袋詰めの時に衛生キャップを被るなどの対策も検討しましょう。出荷の際は目視を徹底し、いかなる異物も混ざらないよう細心の注意を払いましょう。従業員にも徹底させることが重要です。
現実的に最も怖いのが、残留農薬です。消費者の健康にも直結しますし、出荷停止や全量回収などの厳しい処分の対象となりえます。まずは、農薬の使用状況を普段から記録しておきましょう。記録項目は、農薬取締法の省令を参考にしながら、使用年月日・使用場所・使用した農作物・農薬の種類・農薬の使用量は最低限記録しておきます。
そのほか、農産物を加工して販売する場合には保健所の許可(一部は届出)が必要となります。遅くとも「何を売るか、どこで作るか」を決めた時点で保健所に相談します。とはいえ、なるべく早い方が良いですね。保健所は私も行ったことがあるのですが親身になって丁寧に教えてくれました。早めの対応をおすすめします。また、HACCP対応も求められるほか、加工品の場合は食品表示なども厳しく制限されます。
道の駅はビジネスパートナー。地域を一緒に盛り上げていく意識で
最後は少し厳しい内容も書きましたが、安全など最低限のことを守れば、色々なことを試させてもらえるのも道の駅の良いところです。あまり難しく考えすぎず、「とりあえずやってみる」精神は忘れずに直販に取り組んでみてください。それができるのも、道の駅の魅力の1つです。
道の駅は単なる売り場ではありません。道の駅は、あなたと一緒に地域を盛り上げていくビジネスパートナーです。こだわりの農作物が多くの人に届くよう、色々な取り組みを進めていきたいですね。お互いが望むなら、イベント協力やレストラン運営など、農作物の販売以外の取り組みにもつながるかもしれません。
この記事内では大局から細かい施策まで色々と書いたように見えますが、結局は道の駅ごとに特色や考え方の違いがあります。全てに普遍的に通じるマニュアルは存在せず、毎回の販売や駅長からのフィードバックを通じて少しずつ改善していくことになります。困ったことがあれば、いつでもご連絡ください。