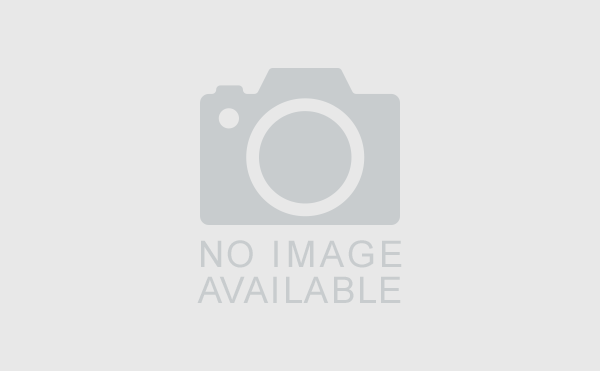農協依存は脱却すべき? 独自販路のメリット・デメリット
Q:農協を通さずに、自分で販路を開拓すべきですか?
A:農協ありきで考えた上で、状況に応じて判断するのが無難ではあると思います。
農協を使うか使わないか
農協は悪という風潮や、六次産業化という言葉の流行など、直販を推奨する声は色々聞こえてきます。そのほか、直販を支援する企業やECサイトの興隆もあり、農協を介する割合は年々低下傾向にあります。ただし、半数以上の農家さんは今でも農協経由で出荷しています。
農協に販売をお願いすることには多くの利点がある一方、農協を通さない販路に活路を見出す農家さんも多いです。販路の確保はマーケティング戦略の最重要事項。経営理念や企業の体力、農作物の特徴・品質、社長や従業員のキャパシティなどを総合的に判断して、経営判断を行います。
農協を使うのは時代遅れ? いえいえ、そんなことはありません
まずは、他の農家さんが農協を使っているかどうかを見てみましょう。農協を通した出荷(系統出荷といいます)の割合は、2020年では64.3%で、2015年の66.2%に比べると少しだけ下がっています(農林水産省「農林業センサス」)。なお、正確に言えば、農産物販売金額 1 位の出荷先が農協である経営体のことなのですが、ここでは概要をご理解いただきたいので粗く表現しています。
ただし、注意しておくべきなのが地域差です。北海道・宮城などは系統出荷が80%を超えていますが、東京は18.9%とかなり低いです。我らが千葉県は50.0%と、半分が系統出荷、もう半分が農協以外の出荷(いわゆる商系出荷です)という形です。千葉県は全国的に見れば農協を通す割合は低いけれど、それでも半分くらいは農協にお任せしているとイメージしてください。
農協を通すメリットは大きい
農協を通すか通さないかは経営判断なので、どちらが良いとか悪いとか言った類のものではありませんが、農協を通すメリットは大きいです。日本の農作物は「作れば売れる」仕組みが整っているので、農家さんがマーケティングに力を入れる必要はありません。その仕組みを支えているのが農協という存在で、販路開拓を代わりに行ってくれる力強い味方です。
「農協は手数料が高い」などと言われがちですが、集荷から出荷まで含めた手数料で、だいたい2割から3割程度。卸売業者の手数料が農協に比べてすごく安いというわけではないですし、ECサイトを見ても大体そんなものでしょう。インターネット直販を利用している農家さんに話を聞いても、「ECサイトを使ったら手数料は高いし、運送会社を使うと配送料は高くて、梱包もすごく大変」といったお話をされます。
※ちなみに販路を考える上では、契約形態にも注意が必要です。百貨店やスーパーとの契約でよく見るのが、消化仕入です。消化仕入では、売れ残りのリスクをこちら側が背負わなければなりません。手数料は表面的には低く見えていたが、「手数料と廃棄損を冷静に計算してみたら、かなりのコストになっていた」といったケースもあります。
手数料だけでなく、買い取ってもらえる金額について考えると、商系出荷は農協に比べて確かに高めです。中でも飲食店や消費者への直販は、中抜きがない分だけ良い値段で売れることになります。しかしその分、お客さんを探す手間だったり、売り場やECサイトの構築やお礼メールの送付、クレーム対応などの「見えないコスト」が結構かかってくるもの。結局、高い値段で売ろうと思えば、それだけのコストが掛かってくるわけです。
世間では「農協=悪」などと平然と言いますが、その善し悪しは私が判断するものではないとして、実際に多くの農家さんが農協を利用して販売しているわけです。千葉県の話に戻ると、首都圏にあって東京にも近くて、高い値段で買ってくれる消費者がたくさんいそうなのに、それでも農協を介した系統出荷が半分というのが現実なんです。それくらい、農協は農家にとって力強い存在なわけですね。
スーパーなどへの販売、消費者への直販も大いにアリ
ここまで農協を通すメリットを強調してきましたが、私自身は農協を通さないメリットも大きいと思います。
メリット① 価格交渉がしやすい
まず思い浮かぶのは価格交渉力でしょう。農協を通した系統出荷の場合、基本的には価格は自分では決められません。
もちろん、農協を通さない出荷にもいろいろありますので、農協を通すか通さないかの二者択一で語れる問題ではないです。たとえば卸売市場へ出荷する場合も(正確には卸売市場の卸売業者。競りor相対取引を経て、仲卸業者や小売業者に二次・三次といった要領で卸されていく)、農家さんが価格を決めることはできません。
一方で、市場を通さない取引をする場合には、基本的には売り手と買い手が価格を交渉した上で、お取引をすることになります。買い手である卸売業者や小売店と農家さんは同じテーブルに着いて、ああだこうだ言いながら価格交渉をします。
別の記事でも書きましたが、「価格交渉できる=高値で売れる」というわけではないです。しかし、市場価格が下振れしても、買い叩かれづらいので、経営の安定化につながります。この辺りは普段からの関係構築にもよるのですが、何となくは想像していただけるかと思います。
メリット② 良いものを高く売れる
甘味が強くてもちもちした食感のバナナをインターネットで売っている沖縄の農家さんを取材したことがあるんですが、その販売価格は取材陣一同が「え~!」と声を上げるほどのものでした。
こだわりの農作物を作っている農家さんにとっては、相応の値段を払ってもらえるかどうかは死活問題です。他の農家さんよりも費用を掛けたいなら、それを上乗せした値段で買ってもらわないと事業を継続できません。これは、価格交渉力があることを前提にして、より上位の難易度のステージにあると言えます。
そこで重要になるのがマーケティングの考え方です。難しいことをしなければならないわけではないのですが、時間とお金がかかってしまうことも事実。こうしたマーケティングを通して、消費者が望むものを、消費者が許容する値段で販売することが求められるわけなんです。マーケティング費用は単なるコストというよりも投資のような性質を持っているので、うまく行けば長期的な成長が見込まれます。
メリット③ 社会のニーズを把握できる
販売を農協に頼らないということは、販路を自分で見つける必要があります。百貨店やスーパーのバイヤー、道の駅の職員やお客さん、インターネットの向こうの消費者とのやりとりに時間を掛けることになるわけです。これはコストである一方で、社会のニーズを知るきっかけでもあります。圃場から出て四苦八苦した農家にしか得られない特権ですね。
社会のニーズが分かれば、ビジネスチャンスにつなげられます。たとえば六次産業化というのは、こうした苦労をした方にしか成し遂げられない飛躍だと私は思っています。社会のニーズが分からないまま当て推量で六次化を進めてしまうと、成功することはほとんどありません。求められていることに向けた六次化には、可能性があります。
経営に活かすために社会のニーズを把握するというのは、少し突飛(あるいは理屈っぽく)感じるかもしれませんが、長い目で見たときには経営的に最も大きなメリットです。本当の意味での「経営者」を目指すなら、消費者ニーズの把握は避けては通れない道。販路開拓は、経営者としての成長スピードを加速させるアクセルでもあると私は思います。
農協出荷にも独自販路にもメリット・デメリットはある
最後は大きなことを言いましたが、農家として最も大事なことは作物を育てることです。「作物は農家の足音を聞いて育つ」「田んぼの肥やしは人の足音」と昔から言うように、圃場に足しげく通うことはとても重要。圃場を蔑ろにしたマーケティング戦略は絶対に成り立ちません。
だから、従業員が少ないうちは、販売はまずは農協に任せて、農作業に専念するのが無難です。規模が大きくなり、従業員を雇い入れた後、販売力を付けていくのが現実的かなと思います。もちろん、作目や経営理念・経営資源、地域との関係性など様々な要素はあるので結論としては個別判断になるのですが、「農協ありきで考えた上で、状況に応じて判断するのが無難です」と冒頭に書いたのはそういった真意があります。
具体的な基準として私が考えているのが、売上高で3000万円~5000万円を超えたあたりです。このあたりで、マーケティングをはじめるのが良いと思っています。そうした農家さんのお力になれるようなサービスをご用意していますので、良ければお声がけくださいね。