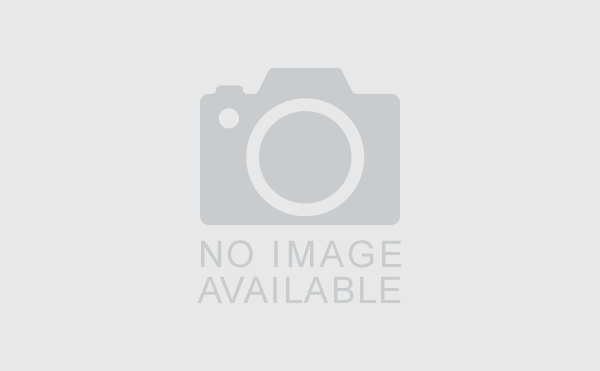Q:作物を何種類か育てているんですが、振り返りや来年以降の計画のために、作目ごとに分けて収支分析をした方がいいですか?
A:やった方が良いですが、時間もかかるので応相談です。投資を行うとき、利益をもっと出したいときはやりましょう。
それぞれの作物が生み出す利益額
売上をもっと伸ばしたい、コストを下げて利益を出したいと考えたときには、現状分析や計画作りを行います。その時に悩ましいのが、作目別に分けて考えた方が良いのかどうか。税理士さんは決算書を作ってくれていますが、その決算書から分かるのは「売上高はいくらで、製造原価と販管費はこれくらい」など、法人全体の数値です。
複数の作物を作っているなら、作目別に収支を分析したほうがいいのは事実。トマトとキュウリを作っているが、来年はトマトの面積を増やそうといった経営判断ができます。正確にやろうと思うと工数は結構多いので、手元のデータを使って、できることからやっていきましょう。
作目別の収支分析とは
作物ごとに、「いくら儲かっているのか」を計算することを作目別収支分析と言います。
たとえば、キュウリとトマトを作っている農家さんの場合、作目別に収支分析をしなければ、今年はちょっと黒字だった、といった情報しか分かりません。税理士さんは決算書を作ってくれたとしても、作目別の売上や利益は教えてくれないからです。
どの作物が儲かるのか、どの作物が手間のわりに利益が薄いのかなどを知るためには、作目別に収支分析をすることになります。「計算してみたら、キュウリの分は赤字だった。トマトがキュウリの赤字額をカバーしているから全体としては黒字だと分かった。来年からはキュウリの面積は減らして、トマトにひとまずは注力しよう」といった経営判断に使えるのが、作目別の収支分析なんです。
作目別収支分析を行うときのポイントは、①分解②記録、の2点です。
①分解
たとえばキュウリとトマトでは共通の肥料も多いです。トマトには200袋を使ってキュウリには150袋を使ったから、肥料費は4:3で考えておこう、といった要領で計算します。
記録さえきちんと取っていたら、あとはエクセルを叩けば良いです。計算することは多いですが、記録することに比べると手間も難易度も格段に低いです。
②記録
記録とは、文字の通り、経営資源の投入量を作物ごとに記録しておくことです。たとえば、鶏糞を年間に1400袋分撒いたとします(これはレシートなどを見れば分かりますよね)。作目別に考えようと思った場合、それをトマトとキュウリにそれぞれ何袋分使ったかを記録しておかなければなりません。
肥料や農薬などの資材であれば、記録されている農家さんは多いとは思います。一番の難関は、労務費です。社長さんや従業員さんの作業時間を、トマトとキュウリに分けて記録している方は少ないでしょう。作目別収支を正確に出すためには、日々の細かい記録がかなり重要になってくるわけです。
それでも、作目別の収支は見ておいた方がいい
確かに、作目別収支分析を正確に行うのは難しいかもしれません。ただ、大体の収支分析であれば、手元のデータから行えます。先ほど、ポイントは①分解②記録の2つであると説明しましたが、「②記録」については来年以降の課題と考えることにしましょう。
いま手元にある情報だけであっても、作目別の収支分析は行えます。「トマトの方が単価は高いけれども収量は低いな。キュウリは収穫の手間はかかるけど、たくさん取れる。結局、どちらが儲かっているかは分からない。来年も今まで通り両方ともバランス良くやろう」という状態を、「データは正確ではないけれども、トマトの方がどうやら儲かっているらしい。来年はトマトの面積を増やしてみよう」という状態には持っていけます。
作目別収支分析は、「ある程度で妥協してとりあえず出す」「ポイントを絞って、来年以降の課題にする」ことが大事です。別の記事でも言いましたが、数字を計算するために農作業を疎かにしたり、睡眠時間を削って体調を崩したりしてしまうのは本当に良くないことです。できることから少しずつやっていけばいいと私は思っていますし、専門的なことは私たちアドバイザーに任せてもらえると嬉しいです。
作目別の収支分析のやり方
作目別の収支の出し方を説明します。キュウリとトマトなど、複数の作目を販売している場合、それぞれの販売額を把握することから始めます。いつ誰に何をいくら売ったかは売上台帳に書いてあることが多いです。もし見方が分からなければ、税理士の先生に聞けば教えてもらえると思います。売上高については、作目別に出すのは難しくはないです。
難しいのは、費用です。キュウリとトマトの場合、同じ肥料や農薬を使うことも多いので、その総費用をキュウリとトマトに振り分けて考える必要があります。この時の分配の基準に厳格な決まりはないので、一番ありえそうな基準を選んで計算してください。たとえば作付面積を基準とします。トマトは6反、キュウリは4反で育てていて、肥料費の合計が300万円だったら、トマトは180万円分、キュウリは120万円分かかったものとして計算します。
続いて、労務費や減価償却費なども按分します。作業日誌を付けていればすぐに分かるのですが、もし付けていない場合には何らかの基準を作って計算します。①作付面積②売上高、などが基準として考えられます。もし余裕があれば、③ストップウォッチを持って、一反あたりの作業時間を計測してみるのはすごく良いです。
基本的には、同じことを全ての費用について行うことになります。決算書にある「損益計算書」に載っている費用を、それぞれ分解してトマトとキュウリに割り振っていく形ですね。
作目別収支分析をさらに正確に行うために
ここまで計算すれば、それぞれの作物(ここではトマトとキュウリ)について、売上高と利益額が(ある程度は)分かります。どの作物が儲かっているかが分かれば色々な経営判断に使えるので、ぜひご活用ください。
ちなみに、この記事で説明したことを真面目にやると、トマトとキュウリのどちらにも当てはまらない費用が出てくるはずです。こういった費用のことを「共通固定費」と言います。税理士さんに支払う支払手数料や借入金の支払利息、事務所の家賃などがそれに当たります。大企業には経理部や人事部がありますが、その人件費なども共通固定費ですね。
その共通固定費は、一旦除外して考えるのがセオリーです。支払手数料や支払利息などの「共通固定費」を考えずに出したトマトとキュウリの利益額のことを「貢献利益」と言います。貢献利益を出すことで、より正確な経営判断が可能になります。たとえば、「キュウリに比べればトマトは儲かっているが、だからといってトマトを圃場全体に植えたとしても共通固定費をカバーするだけで精一杯だから会社全体の利益は実はそれほど大きくならない。販売力を強化したり、キュウリ・トマトではない第三の作物を植えなければならない」といった経営判断につながるわけです。
と、最後は複雑な話になりましたが、作目別の収支分析は、最初の一歩としては粗いものでも構いません。それでも経営的には大きなプラスになるはずです。
より正確な作物別収支分析に向けては、煩雑な計算や記録が必要となります。時間が足りない方は、外部のサポートを検討するのも一案です。アドバイザーとしてお手伝いいたしますので、いつでもお声がけください。