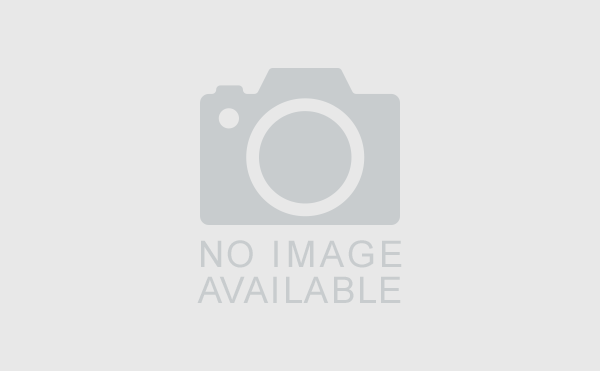経営指標って、どうやって使うの?
Q:経営指標って何のために見るの?
A:仮説を立てるために見ます。
経営指標とは
経営指標とは、会社の経営状態を数字で表したもので、たとえば自己資本比率や売上高経常利益率、債務償還年数、1人当たり売上高などがあります。
経営者の方なら一度はご自分の経営指標を見たことがあるでしょう。経営指標を無料で出力してくれるサービスに財務データを入力すると、「この農場の総資本回転率は0.7回で、業界平均値に比べて0.15回分少ないため、望ましくない経営状態です」などと表示してくれます。
それを見たあなたは思います。「え、だから何?」「業界平均から劣ってるから何なんだよ」と。納税のために作った決算データを、せっかく作ったのだから経営にも活かしたい。けれど、使い方が分からないから見て見ぬふりをしてきたという方も多いはずです。
経営指標の計算方法
ご自身の会社の経営指標を出したことがない方がいらっしゃったら、まずは一度計算してみてください。といっても電卓やエクセルで算出するのは面倒なので、無料のフォーマットを使うのがおすすめです。公的なところでは経産省がローカルベンチマーク(通称ロカベン)を公開しています。ロカベンで分かるのはすごく簡易的な結果なのですが、その分入力もすごく簡単なので15分くらいでできます。
経営指標に意味はあるのか?
経営指標は、使い方によっては、ある程度の意味はあります。指標を算出すること自体は難しくないのですが、問題なのは「それをどうやって使うか」です。少し工夫が必要です。
たとえばキュウリやトマトなどを露地で作っている農業法人の自己資本比率が10%だったとします(他の業種から見るとかなり低く映りますが、農業法人だとよくある数値です)。自己資本比率というのは借金に依存しすぎているかなどを見る指標なのですが、10%というのは借金が結構多くてヒヤッとする数値です。業界平均16.5%(日本政策金融公庫の資料から)なので業界水準と比べても低めです。
さて、ここからが重要です。「自社の自己資本比率がまずい状況にあるらしくて、業界平均を下回っているらしい」というデータを、どのように使えばいいのでしょうか?
ここでつまづいてしまう人が多くいます。というか、経営指標を経営にうまく活用できているケースは本当に少ないと感じています。
よくある例として思い浮かぶのが、業界平均との優劣を比較して喜んだり悲しんだりすることです。これは、ほとんど意味がない。むしろ、落ち込むだけで終わらせるなら、精神衛生上良くないので見ない方がマシ説までありえます。経営指標というのは自分を鼓舞したり悦に浸ったりするために使うツールではありません。本当はもっと有益な使い方があります。
※
ちなみに、業界平均との比較自体に意味がある場面も無くはないです。たとえば銀行員が与信判断をする時には、業界平均は効いてきます。なぜなら、銀行員のお仕事の1つはお金を確実に回収することだから。業界平均から見て成績が悪いことは、それ自体で懸念材料になりえます(それなら同業他社に貸したいと思うのが銀行員)。だから銀行員などの外部者にとっては平均値との比較はすごく重要になりますが、経営者の皆さんは「数字が悪いから経営を諦めよう」という判断はできないので、単に比較することに意味はありません。
経営指標は、仮説を立てるために使え
私たち専門家も、経営指標はそれなりに見ています。私たちは数字のプロなので生の決算書を見ればだいたいのことは分かるのですが、抜け漏れがないか確かめたりアドバイザリー業務を効率的に進めたりするために補足的には使います。
農家さんや農業法人の経営者の皆さんに私がおすすめする経営指標の使い方は、「仮説を立てるために使え」です。仮説を立てるために使うなら、経営指標というのはすごく有用です。無味無臭の財務諸表に匂いがついて、強みを伸ばすべきポイントや注意点などが自然に立ち上がってくるのです。
実際には、こんな感じで使う
ここからは、実際に経営指標を使って考えてみましょう。お時間のない方は結論までジャンプしてもOKです。
一例として、有形固定資産回転率という経営指標を考えてみます。年間の売上高が6,000万円、トラクターや播種機などの「有形固定資産」が5,000万円なら、有形固定資産回転率は1.2回です。先ほどの政策金融公庫の資料によれば平均値は1.9回なので、これはかなり悪い数値です。
これは、有形固定資産がたくさんあるわりに、それが売上に繋がっていないことを意味します。つまり、お金をかけて投資したのに、それが結果につながっていない状態です。
そこで、投資効果が出ていない原因を考えて、仮説を立てます。たとえば「人手不足だから、頑張って投資した設備がフル稼働していない」という仮説は容易に立てられます。この仮説を見つけるのが結構難しいのですが、経営指標を見れば当たり前のように導き出せますよね。
この仮説が正しいのかどうか、つまり「本当に人手不足なのか」は、現場を見ながら判断します。ところが、圃場を観察してみたところ、人員の割り当て自体は問題なくできていることが判明しました。売上高に占める人件費の割合を見ても30%と、平均値と大きな差異はありません。ということは、先ほどの仮説は間違っていたということです。
そこで、次に「圃場面積に比べて機械設備に金を掛けすぎている」という仮説を立てました。今回は現場に出る前に、この仮説の確かさを見るために別の経営指標を見てみることにしましょう。そこで見るのが、10a当たりの機械装置・運搬具です。平均的には、10aあたりの機械装置・運搬具は13.2万円ですが、自社の場合は21万円と、大きく上回っていました。「圃場面積に比べて機械設備に金を掛けすぎている」という仮説は、経営指標を見る限り結構ありえそうな仮説です。
ということで圃場に出て、この仮説を検証していきます。まず確かめるべきなのは機械設備の稼働率でしょう。全自動播種機の稼働時間を計測して、それを全ての圃場で使ったらどうなるかを計算してみることにしました。。。
といった要領で、仮説を次々に立てて、利益が伸びきらない理由を探っていきます。
おそらく、現場での作業だけで、機械装置・運搬具に注目することは中々難しいのが現実でしょう。注目したところで、その機械装置の金額が経営全体に占める意味を理解することは難しい。「減らせるなら減らした方がいいよね」という安易な考えで意味のないコストカットをしてしまっては経営に悪影響を及ぼしかねません。会社が抱える課題や解決策が直観的に分かるなら敏腕経営者だと言えますが、そういった経営者の勘に頼らず課題を明らかにしようと思ったときに使えるのが経営指標なんです。
経営指標を目印にしながら仮説を立てて検証していくと、課題に正しくたどり着きやすくなるはずです。課題が分かれば対策を打てます。上述したのは一例ですが、こんな要領で経営指標を使ってみてください。
【結論】経営指標は、財務を紐解く目印になる
せっかく手元に決算データがあるのだから、これを有効活用しない手はありません。しかし、財務分析のやり方なんて分からない。。。そんなあなたにとっては、経営指標が大きな手助けになってくれるはずです。
繰り返しになりますが、他社より数字が悪いからダメだ、などとつまらないことに頭を抱える必要は全くありません。もっと利益を伸ばしたり、もっとみんなを喜ばせたり、前向きに経営指標を使いましょう。
まずはロカベンを使って自社の経営指標を出して、仮説を立てて、経営課題の解決に使ってみましょう。もし分からないことがあればいつでもご相談ください。